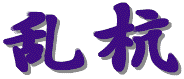 |
発 行:ひょうすぼ社 |
|
|
|
私的新聞 乱杭192号(2004年10月20日)
乱杭読者も、そう思っていらっしゃいませんか?
●「織田信長墓所」 今回の3日間お世話になった個人タクシーの運転手、中塚祥三さんによれば、基本的には旧本願寺は光秀の襲撃によってことごとく焼き尽くされ、信長の遺骸の所在すら判然としない状態であったので、その地の灰などが祭られていて、1箇所は、秀吉によって葬儀が行われた寺など、信長の墓所とされる所は、現在3箇所あるのだそうだ。
●「西本願寺書院」と「飛雲閣」 我が家の宗旨は、浄土真宗本願寺派である。つまり、西本願寺は、我が家の菩提寺の本山である。 ●鞍馬寺本堂の「張り紙」 191(2)の添付写真上段の張り紙をもう一度ご覧下さい。これは、鞍馬寺登山ケーブルカーを経由して本道の足元まで行き、ケーブルカーの終点からトボトボと途中の休息所で休んだりしながら、ようやくたどり着いた本道の東入り口に入ったその場所の正面の板壁に、無造作に貼りだしてあった。 私は、今の世のテロや民族紛争を基本的には「宗教の恐怖」と考えている。なれども、その根幹に「石油利権」などが複雑に絡んでいることも知っている。 テロはやめよう 戦争はやめよう 無慈悲で残酷だ 真の平和を願って ひたすら祈ろう 鞍馬寺
こんなに率直な平和への呼びかけを、寺、神社めぐりが好きな私も、これまでに見たことがない。 日本の宗教者は、遠慮せずに、その影響範囲で、平和や人の命の尊さ、無差別殺戮や親子殺し、兄弟殺しの不条理、人種・門別差別の理不尽、人が人を迫害することの愚かさ、醜さ、間違いをもっと声を大きくして門徒人民に問うべきではないか。 それが宗派を問わず、宗教者の勤めのように思える。 ならば君は、と問われれば、恥ずかしながら、鞍馬寺で出会ったあの貼り紙に即座に反応した自分を「ほめてやりたい・・・。」と思う 程度です・・・ ●祇園巽神社など 3日間、見て回りたいところをスケジュール表にする。 2日目に訪れた「曼殊院門跡」や最終日の「巽神社」「南禅寺境内の『水路閣』」は、その典型です。私はこれらを全くノーマークでした。 中高年向け雑誌「サライ」でもカバーしきれない、中高年ピッタシの観光スポットが、まだまだ埋もれているのが「京都」という町の奥深さのように思えます。 ●ぎんもんど この日に昼食として「湯豆腐ひととり」約3000円を頂いた「無燐菴」西隣の「ぎんもんど」もそんな運転手さんから紹介していただいたお店でした。もう、野菜のてんぷらが最高でした!
●田中漬物店 1970年代、大阪府吹田市千里山の公設市場に漬物屋さんがあって、漬物の好きな私はそこであれこれ漬物を買っては食べていました。 以来、生活費に窮したら、これを買ってご飯とこの漬物で飢えをしのぎました。兎に角美味しかったという記憶しかありません。 その「からし菜」が宮崎にはなく、インターネットを介して探していてであったのが「田中漬物店」です。 そんなご縁で今回、最終日の飛行場への帰路、寄らせていただきましたが、寄らせていただいたお陰で、京都の町衆が引き継いでこられた「観光案内書」には書かれていない「町の祭り(粟田神社例祭)」を見ることができました。これも今回の大きな収穫でした。 次は、何にこじつけて両親を京都へ引き出すか、思案投げ首です。
やっつけ仕事で一丁上がり、みたいな手抜き仕事になりそうです。
乱杭191号(1)〜(3)に記述した今回の親子3人京都旅行報告は、
その最たるものでしょう。
そんなこんなで申し送れましたが、今号で、
若干の補足説明をさせていただきます。
乱杭191号(1)添付した信長廟の写真の左手奥に、信長と共に本能寺で遭難した家来約100名の名を記した高札があり、その中に森蘭丸の名もあった。仮に、若干生き延びることが出来た家来があったとしても、明智勢は1万〜2万と言われ、これを「多勢に無勢」というのであろうと納得した。
秀吉が造営した聚楽第の一部を移設したと伝えられる書院と飛雲閣を見るためには事前に西本願寺のその向きの部署に電話で予約をいておく必要があり今回、初めて見た。
台風22号の被害を恐れて、飛雲閣は薄板で外部が覆われていたりしたが、国宝の書院「鴻の間」から見た東能舞台など、そのすばらしさは、ここで表現することもできない見事な建物であった。
というより、日本の宗教界は、いつかの出来事に懲りて、所謂「羹に懲りて膾を吹く(あつものにこりてなますをふく)」状態となり、これらの問題に、意図的に口を閉ざしているように思え、この鞍馬寺本堂内の貼り紙に強烈に感動した。
そして、初日にタクシーの運転手さんに渡して、「このスケジュール表の見学場所の近所や経路に、ここも寄って見ればいいのに。」と思われる所がありましたら、どうぞ寄ってください。」とお願いしている。
ある時「からし菜」という九州宮崎では聞いたことのないお漬物があり、買って食べたら、美味いのなんの・・・。
何代目かの店主(?)、岸義人さんがホームページを作っていらして、そこを介して色んな京都とお漬物の話を教えていただきました。
|
|
|
|
|
|